武士道の名著「葉隠」から。武士とは死に物狂いになることなり。誰でも一度は武士になっている。(2025年11月11日公開)
- chibamai
- 2025年11月11日
- 読了時間: 4分
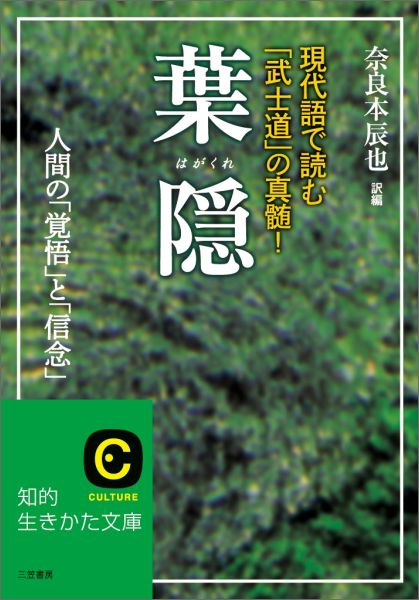
誰でも受験・試合・仕事などで死に物狂いになったことがあると思います。
この本、
『葉隠』(はがくれ)は、江戸時代中期(1716年ごろ)に書かれた書物。肥前国佐賀鍋島藩士・山本常朝が武士としての心得を口述し、それを同藩士田代陣基が筆録しまとめた。(wiki)
となります。鍋島藩は特に優れた藩主を歴代生んで有名でした。
武士道とは、宗教でも道徳でもない、と現代語訳者の奈良本達也さんは前置きで書いていますが、当方の印象ではキリスト教やイスラム教穏健派によく似ていると思います。
宗教では神に仕えます。武士道は主君に仕えますが、勿論神ではなく時として欠点だらけの人に奉仕しなければなりません。しかし「仕え方」は宗教も武士道も同じではないでしょうか。
自分を低くして謙虚になり、全てを捧げるという仕え方です。
奈良本さんはこうも言っています。「この本は人間の生き方を教えている。死を覚悟することがそのまま生につながる。死を生に転化する方法として、死の覚悟がある」これは究極のスピリチュアリズムだなぁと思います。
さて、葉隠から気になった文を抜き出していきます。
奉公人(武士)の修行というのものは、おれ以上の者はないと思いあがるほどでなければ役に立たない。それだけの心がけが必要である。
武士道の4つの誓願。毎朝神仏に祈る
1 武士道において絶対に遅れをとらないこと(自分を磨く)
2 主君のお役に立つこと
3 親に孝行すること
4 大慈悲心を起こし、人のためになること
一日一日、その日を最期の日と決める。今このときに全てがある。
武士道とは死ぬことである。生か死かいずれか一つを選ぶとき、まず死を選ぶ。
人間はいつ死ぬかわからない。現実とは夢の中で遊んでいるようなもの。その日その日を最期と思い定めて主君のために役目を大切に実行する。
武士道とは死に物狂いそのもの。
自分の一生の仕事は、ただ人のためになることをすればよい。
いまがいざ、いざがいま、二つを分けない。今の今を一心不乱に生きる。現在という瞬間を最高に生きる。
一年発起すれば天地をも突き通す。何ごとも不可能はない。
40歳までは何事も強く進み出るがよい。しかし50歳が近くなると、控えめにするのが正しい態度。
(武士道などの)道というのは自分の悪いことろを知ること。いつも反省して一生かかって努力しなければならない。
勝敗について。勝たなければと思うと勝てない。なりふり構わずただひたすらに突き進むと、そこから本当の自分が蘇ってくる。
人目を引くような武士は本物ではない。武士として主君を思うより他のことは考えなくてよい。
武士のありかたとは。自分の身命を惜しみなく主君に差し上げる。身を修めて智・仁・勇の三徳を備える。
武士の出世は大器晩成でよい。50歳ごろからゆっくり才能を磨き上げればよい。
才能は、10のうち3つか4つはしまっておく。不器用でも実直であれば、立派に奉公できる。知恵のある人間は全て理屈で通用すると思うのが間違い。そして勘定高い者は卑怯である。いつも損得で考えるから。
私利私欲のために立ち働くものはいつか失敗する。
どれだけすぐれた才能があっても、人に好かれぬ者は役に立たない。
主人を諫言(かんげん)する(いさめる、忠告する)ことは大切。聖君とか賢君は、よく諫言を聞き入れる。だからお家が安泰になる。
人とのつきあいかた。ほめることは重要である。落ちぶれた者に対しては、あれこれと気をつけてやり、どうかしてその者が立ち直るようにしてやるのが、侍の義理である。
酒の飲み方ー武士が気をつけるべきは大酒、自慢、奢り。
特に幸せなときは、自慢と奢りに気をつける
自分の心は、自分に対する見張り役。
人間は苦しみを経てきた者でないと根性がしっかりしない。若いうちは苦労するに越したことはない。(注、格言:若い時の苦労はカネを払ってでも経験せよ)
ーーー
当方が気になったポイントは以上ですが、人によってはそれぞれあると思います。
例えば、くしゃみが出そうになったら額を押さえるのだそうです!知りませんでした。
ちなみにちょっと前までの日本社会に「モーレツ社員」というのがありました。会社のために全てを捧げ、家庭も顧みずにモーレツに働く姿です。これなどは武士道のアレンジ編かもしれませんが、美学ではありませんでした。出世したいという私利私欲がからんでくるからです。そして日本経済のバブル崩壊とともに、会社に忠誠を誓ってもどうしようもないことが分かったのです。
もう一つ、「女性は夫に、主君のように仕えなければいけない」というのも武士道でしたが現代は西洋文化の影響で、これも消え去ろうとしています。
何が残って何が消えていくのか、これも時代の移ろいです。



コメント